小説目次
ボタンをクリックすると開きます
七月初旬。
教師に促されて、僕は教壇の前に立つ。
初めて通う学校、初めて見るクラスメイトの顔。
だが僕自身にとってはこれが最初の経験じゃない。もう慣れたものだ。
小学校の間に三回の引越しを経験し、中学生になってからはこれが一回目。計四回。転校に関してはちょっとしたベテランなのだ。
たくさんの好奇の視線を受け止めながら皆に挨拶をする。
十四歳相応の、適度に緊張した様子を見せながら、まず名乗る。趣味を言い、今まで過ごした学校を挙げ、この教室に一刻も早くなじみたい旨を述べてから、少しあわてたようにお辞儀する。
これで問題なし。特に可もなく不可もなく。その場をやり過ごすためだけの無難な挨拶。何の引っ掛かりも残さない。
暖かい拍手を浴びて、僕ははにかんでみせる。
これからほんのしばらくの間よろしく、と思いながら。
僕がその携帯ゲーム機とソフトを手に入れたのは小学五年生の春だった。
確か三度目の引越しが終わったばかりだったと思う。
父親の荷物をまとめたダンボールを開けた途端、それが転げ落ちたのだ。箱の中でどのように引っかかっていたのかは分からない。
最初に見たとき、僕はそれが携帯ゲーム機だとは思わなかった。
なにしろそれは弁当箱のように大きかった。それも薄型の生っちょろい奴ではなくて、ドカ弁タイプである。その頑丈な凶器めいた角がフローリングの床に当たってゴツリと鈍い音を立てた。
ちょうどそばにいた父親が、それがゲームに使う機械であると教えてくれた。
「ゲームセンヨウキ? これが?」
「お前が生まれる前に出たゲームだよ。そうか、これが何なのか、もうわからない世代なんだなあ」
父親は変にしみじみした口調でそう言った。
「まあね。そもそも興味ないし」
僕は素直に思ったことを言った。
「だいたい、ゲームなんて、根暗でオタクで足の臭そうな奴のやることだからね」
僕の言葉に父親はちょっと傷ついたようだったが、実際はどうだったかは分からない。だいたい彼はあまり表情を動かさない。
ゴミ袋を両手に持った妹が通り過ぎざまに言った。
「じゃあ、あんたにぴったりじゃん」
「うるさい黙れ」
と、僕は言った。
そして、ドタバタした、嵐のような引越しの荷解き作業の時間が過ぎ去ったとき、僕の手元にはその携帯ゲーム機と一本のソフトが残った。ちょうど潮が引いて磯のくぼみに小魚が取り残されたような具合に、自然の流れで、僕はその古いゲーム専用機の新しい所有者となったのだった。
そのことについて父親は何も言わなかった。たぶん忙しさの余り、忘れてしまったのだろう。
僕自身も忘れていた。
数日たってから、夜寝る前にそのゲーム機のことを思い出し、なんとはなしに手にとった。電源を入れてみたが動かない。調べてみると、乾電池で動くらしいということがわかった。乾電池が動力? そんな奇妙なゲーム機は聞いたことがない。
居間の
驚いたことに、ゲーム画面は白黒液晶だった。
まあ、目には優しいのかもしれないな。僕は思った。
ところがさらに驚いたことに、ちっとも目に優しくないのだった。
キャラクターに合わせて画面が動くと、背景が墨を垂らしたように滲み、流れるのである。
スタートボタンを押すと、「魔界天使GIGA」というタイトルと、プロローグのテキストが下から上にスクロールしていくのだが、その文字がすでにぼやけているのだった。
いくつもの せかいを ないほうして はしる ふしぎな れっしゃ
れっしゃの どこかには きょまんの とみが かくされている という
ざいほうの うわさを しんじて おおくの ものたちが
れっしゃないの たんさくに のりだした
だが かれらの うんめいを しるものは いない
そして いま また ひとり…
なるほど、それが僕ってことか。どうでもいいけど、曖昧でふわっとした世界設定だな。
心の中で突っ込みを入れながらゲームを始めた。
そして……ふと気づくと、窓の外は白々と明るくなっていた。
生まれて初めて徹夜した。夢中になってしまったのだ。
結局僕はその日の授業を絶えまない睡魔と戦いながらやり過ごした。ゲーム機は学校には持っていかなかった。そんなものは無駄に目立つし、馬鹿でかくて持ち運ぶことなど思いもよらなかった。
だから、ただひたすら学校が終わるのを待ちわびて、早く家に帰り、部屋のベッドに寝転がってそのゲームをプレイした。
乱暴で、殺伐とした、素晴らしい世界。
主人公は仲間とパーティーを組み、その巨大な列車の中を旅していく。
モンスターとの戦い、新しく出会う人間たちとのやりとり。そして少しずつ明かされる列車の秘密が僕を魅了した。
よくよく考えてみれば奇妙な話だ。僕はそれまでゲームなどほとんど触ったことがなかった。そんなものに費やす時間があるならもっと他のことをしたい、そう考えるような人間だった。
それなのに、二十年以上も昔のゲームに夢中になってしまうなんて。
ネットにも繋がっていない、きわめて旧い世代のゲーム機。
メモを取らなければ、電源を消した途端に何もかも消滅してしまう。
それは完全に閉じた、あまりにも儚い世界だ。ひょっとすると手軽でチープだからこそ、僕はそれに熱中したのかもしれない。自分自身の手で何とかすることができるから。例えできなくても、セーブしてスイッチを切ってしまえばひとまず保留にできる。
電源オフ、終了。
だがこのゲームには、最後の最後に、とんでもないバグが隠されていた。それまでの苦労を、感動のストーリーを一発で台無しにするひどい不具合だ。
列車の先頭まで進んだ主人公と仲間たちは、列車を作った創造主、つまり世界を創った神様と相対する。
神こそ悪であり悪魔を体現した真の神すなわち人類の敵だったのだ……という理屈で最後の戦いが始まる。
このゲームで主人公が使える最も強力な攻撃技は「奥義暗黒吸魂輪掌破」という名前を聞いただけで背筋がぞわぞわする必殺スキルだが、これを当てても神は倒せない。もううんざりするくらい通用しない。ヒットポイントと防御力が最高値に設定されていて異様に『硬い』のだ。
ところが、最初のエリアで装備できるトンカチという最弱の武器を使うと、あっさり撲殺できてしまうのである。ただ一撃で。
ネットで調べた情報によると、バグが残ってしまったためのチート技なのだという。
そもそもトンカチって武器じゃない。日用品だ。
そんなもので世界の創造神が死ぬなんて、物語の盛り上がりも何もあったものじゃない。ひどすぎる。ヒロインの痛ましい死やライバルとの熱い共闘は何だったのか。
そんなのってないと思う。
「それは脚気だな」
ヤスヒコは断言した。
「カッケ?」
不意に出てきたその単語はその時の状況からはあまりにも場違いだった。僕たちは食堂でスパゲティ定食を平らげたばかりで、窓際の席に座ってリンゴのジュースを飲んでいた。
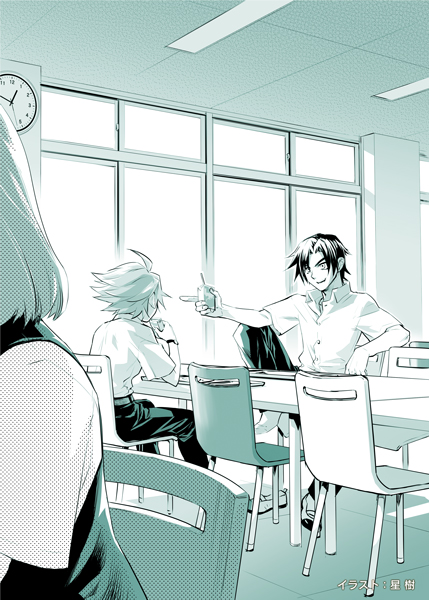
「ビタミンが足りないとかかる病気。小学生のときに検査しなかった? トンカチで膝小僧を叩くんだ。知らない?」
「それはわかるけど。なんで脚気?」
ヤスヒコは窓の方を向くと、しばらくの間、目を細めて校庭を眺めていた。何か深遠な事柄に思いをはせているような面持ちだった。やがて僕のほうを見て言った。
「だって、トンカチに意味があるのって、それくらいしか思いつかないしなあ……」
「なるほど」
僕はうなずいた。
それからしばらくの間、脚気の検査に引っかかって神が即死するというしょうもないイメージが僕の頭から離れなかった。
ヤスヒコとはクラスが違った。彼と初めて顔を合わせたのは、僕が転校してから二週間後のことだ。
全校生徒が借り出されて、夏休み前の閉校式のためにさまざまな作業をさせられていた。
僕たち一組は体育館いっぱいにパイプ椅子を並べるという世にも面倒な作業を行っていた。
作業の指揮をとっていたのは生活指導の男の先生で、彼はステージの中央に陣取り、体育館を
僕はまじめに従っている振りをして椅子の間をウロウロしていたが、不意に、この作業をつい最近やったことがあると感じた。
しかし、どこで?
すぐに気づいた。
「GIGAみたいだな」
僕は思わずゲームのタイトルを口に出してつぶやいていた。
「GIGA」では四つの宝珠を集めることがストーリーの進行上必要になってくる。そのうちの二つ目を手に入れるイベントで、無数のダミーが敷き並べられた部屋から、正しい宝珠を見つけ出す、というシーンがある。これがまた難問で、手がかりに気づかないと、しらみつぶしに一歩ずつ「探す」羽目になる。
このシーンに、今の椅子並べが似ている、と思ったのだ。
言ってしまってから、やっぱりあんまり似ていないかも、と思い直した。椅子を無数に並べる作業と、正しい宝珠を一つだけ見付け出すのは全然違うな。そう思った。
だが、背後にいた少年が口を開いた。
「今GIGAって言った? 『魔界天使GIGA』のこと?」
僕は椅子を運ぶ手を止めて相手を見た。まさかそのタイトルを他人の口から聞くとは思わなかった。
長身で精悍な面構えの男子生徒だった。少年というよりはむしろ青年と言ったほうがふさわしいのかもしれない。僕とは身長差が十センチ以上はありそうだった。
それが人なつっこそうににこにこと
「ゲーム好きなんだ? 俺も好きなんだよー」
それがヤスヒコだった。
転校して一月も経たないうちに夏休みに入った。
僕は家の近くにある市民図書館に出かけて時間をつぶした。
本を読むわけではない。本なんて読むのは時間の無駄だ。世の中にはもっと楽しいことがたくさんある。
僕にとっては、図書館の蔵書よりも、図書館の前面に広がるレンガ舗装の広場の方が魅力的だった。ちょっと体を動かすには最適の運動場だ。
小学校一年生のとき、僕はサッカークラブに入っていた。
引越しで辞めてしまったが、当時教えてもらったリフティングだけは妙にうまくなった。
適度なスペースとボールがあればひとりでずっと楽しめる。そういうところが性にあったのだろう。
リフティングと言うのは、技術もあるだろうが、要は慣れの問題だ。ボールに慣れることができれば、技術はあとからついてくる。百回くらいできるようになると視野が急に広がる。そうなると、リフティングする→たくさんできる→楽しい→リフティングする→たくさんできる→……無限ループの出来上がりである。
その日の夕方近く、僕が広場でボールを蹴っていると、数人の男子生徒がぞろぞろと出てきた。
僕は気付かないふりをしてリフティングを続けたが、彼らの視線を感じた。
やがて一人が僕の傍らにやってきて声をかけた。
「うまいもんだな」
僕はボールを踏んで止めた。
「リフティングだけならね、自信があるよ」
「君、夏休み前に引っ越してきたんだろ?」
「うん、そうだよ」
「オレと同じクラスだ」
「あ、そうなんだ。よろしくね」
僕は快活に笑い、自己紹介しあった。相手に本性を見抜かれないように。
「それだけうまいんなら、サッカー部に入れば?」
と、相手は言ったが、僕は首を振った。
「さっきも言ったけど、得意なのはリフティングだけなんだ。それ以外は全然駄目。だから、これはただの趣味みたいなものさ」
「へえ」
それで会話は途切れた。
「じゃ、また。二学期によろしくな」
「うん、じゃあね」
僕は手をあげて彼らを見送った。彼らは五人だった。
その中にヤスヒコの姿があった。
急に、もう笑いたい気分ではなくなった。
やはり何度考えても奇妙な話だ。父親からもらった『魔界天使GIGA』がきっかけで、僕はヤスヒコと話をするようになった。
そして、ヤスヒコに誘われて、ネットゲーム『The World』を始めたのだ――今の僕にははっきりとわかっている。僕の運命は自分ではまだそれがどうなってほしいかも考えていなかったうちに完全に決まってしまっていたのだと。
後になって知ったのだけれど、ヤスヒコが『The World』に誘ったのは僕だけだった。
ヤスヒコはどうして僕を誘ったのだろう?
僕はこのことを何度も何度も繰り返し考える羽目になった――彼に直接尋ねることができなくなってしまったから、余計に。
この物語は僕が中学二年生の時、二〇一〇年の秋に始まり、同じ年のうちに終わる。ひょっとすると、多少はみ出たり前後したりするかもしれない。けど、まあやってみよう。
電源オン、「世界」の始まり。
(続く)